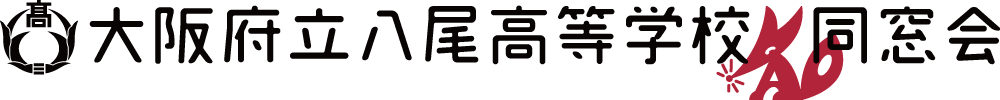ゆうかり文庫(出版情報)
新版 債権総論 下巻
出版日2022年03月28日発行者判例タイムズ社 著者奥田昌道(高3期)、佐々木茂美(高18期)
下巻の取り扱う範囲は、上巻・中巻で取り上げた部分の残りである「第5章 債権譲渡と債務引受」と「第6章 債権の消滅」であり、その分量は中巻とほぼ同程度になる。
旧版を基底に据えながら、旧法下における判例法理を整理するとともに、法制審議会の審議過程における議論を参酌して新法の下で想定される裁判・弁護実務上の諸課題を取り上げ、その解決の方向性を探ることは、難しい作業の連続であった。
新法下において生ずる解釈上の諸問題については、更なる議論の深化がみられるところであり、今回の改訂作業において十分に咀嚼することができなかった問題点等も含め、少し時間をおいて考察してみる機会もあるのではないかと思っている。
佐々木茂美(高18期) (「下巻の刊行に当たって」より抜粋)
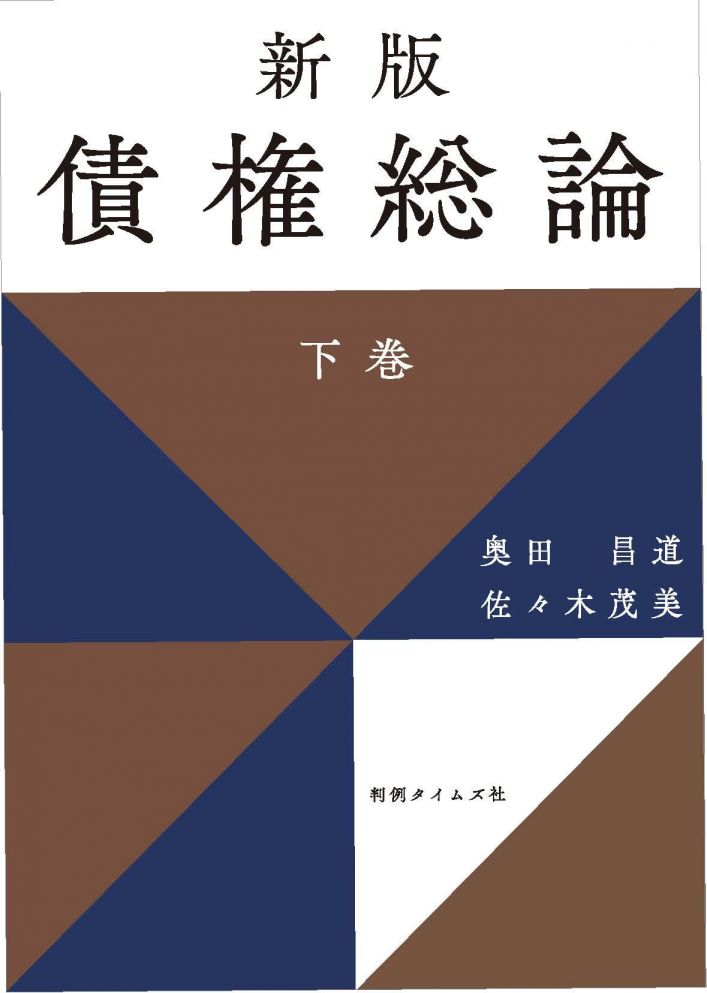
奥田昌道(高3期)、佐々木茂美(高18期)
奥田昌道(高3期)
1932年生まれ
1955年:京都大学法学部卒業
1958年:京都大学法学部助教授
1970年:京都大学法学部教授
1992年:京都大学大学院法学研究科教授
1996年:京都大学名誉教授
1999年:最高裁判所判事
2004年:同志社大学大学院司法研究科教授
同年:日本学士院会員
佐々木茂美(高18期)
1948年生まれ
1971年:京都大学法学部卒業
1974年:福岡地方裁判所判事補任官
1988年:東京地方裁判所判事
1989年:司法研修所教官
1999年:大阪地方裁判所部総括判事
2005年:京都家庭裁判所所長
2007年:大阪地方裁判所所長
2010年:司法研修所所長
2011年:高松高等裁判所長官
2012年:大阪高等裁判所長官
2013年:京都大学大学院法学研究科教授
新版 債権総論 上巻
出版日2020年06月28日発行者判例タイムズ社 著者奥田昌道(高3期)、佐々木茂美(高18期)
『債権総論(増補版)』(1992年・悠々社)の前身は,『債権総論(1)上』(1982年),『債権総論(1)下』(1987年・共に筑摩書房)であり,平成4年(1992年)に合本するに際し、若干の加筆・修正を施して,新たに悠々社から刊行されたものである。
早いもので、『債権総論(増補版)』(以下「旧版」と略)から数えても、既に28年が経過している。
この間、社会経済情勢が激変し、法制度や法理論にも著しい進展が見られ、それが今般の債権法制等、民法改正に結実した。
このような状況の下で、かねてより旧版を改訂したいと考えていたところ、幸いにも、長年にわたり参加している「大阪民事実務研究会」において親交をいただいていた佐々木茂美氏(元・大阪高等裁判所長官)が、退官後、京都大学大学院法学研究科教授に就任されたのを機に、平成26年(2014年)秋頃から,ほぼ1か月半の頻度で同氏と共同研究会を持つようになった。平成28年(2016年)7月までには、「第2章 債権の目的」について「第5節 利息債権」を除く部分と、「第4章 多数当事者の債権関係」について第1節辺りまで検討を進めていたが、公私にわたる諸般の事情から中断するに至った。
その後、平成30年(2018年)1月、佐々木氏から改めて新しいコンセプトの下に改訂することを勧められた。その基本的方針は、旧版を基底に据えつつも、それに大幅な修正・加筆を施すことによって、現在の法実務の状況に適合する最新の判例法理等の情報を提供するとともに、この分野を学習する者、とりわけ法科大学院生や司法修習生、さらに法曹等の実務家や研究者にとっても実践的な内容のものとすることであった。
奥田昌道(高3期) (「『新版 債権総論』の刊行に当たって」より抜粋)
本書の改訂作業に関わったのは、次の2つの想いからである。
1つ目は、長年の公私にわたる奥田先生の御指導、故事に倣い「過分の恩」というのであろうが、これをいつかお返ししなければならないとの願いがあったことである。というのは、私事ではあるが、奥田先生は、昭和 42年(1967年)の大学入学当時、健康を害していた私を慮り、高校の後輩というだけで、御自宅の2階に下宿させて下さり、奥様と共に日常生活万般にわたり誠に行き届いた細やかなお心遣いをいただいた。お蔭で、私は、健康を取り戻し、その後の39年間の裁判官生活を終えることができたし、この間においても、「大阪民事実務研究会」を始めとする様々な機会に御指導御鞭撻を賜った。
2つ目は、私が、平成25年(2013年) 4月から5年間, 京都大学大学院法学研究科において、実務家教員として、実体法・手続法の研究者による学問上の成果を採り入れ、逐次教材を刷新しながら、学生諸君との対話、研究に専念することができる機会に恵まれたことである。このように教育と研究に没頭できたことから、法律実務家にとって、法が対象とする社会、経済等の激変に伴う事象の多様性と多層性に踏み込み、その成り立ちを法的に解き明かすためには、法の原理や理論が具体的な問題解決の場面でどのような役割・機能を果たしているかを確認することを通して、今一 度、法制度全般の体系的な理解に立ち返ることが肝要であると考えるに至った。折しも、大学の先輩である故田原睦夫氏(元・最高裁判所判事) から債権法改正の勉強会にお誘いいただき、その際に、本書旧版について、「法理論とりわけ判例法理の展開等を加えたものにならないか」との御示唆を受けた。
このような経緯から、学理の1つの到達点を指し示す大著である旧版を上記のような視点から改訂することを先生に提案し、御了承をいただいた。
佐々木茂美(高18期) (「上巻の刊行に当たって」より抜粋)
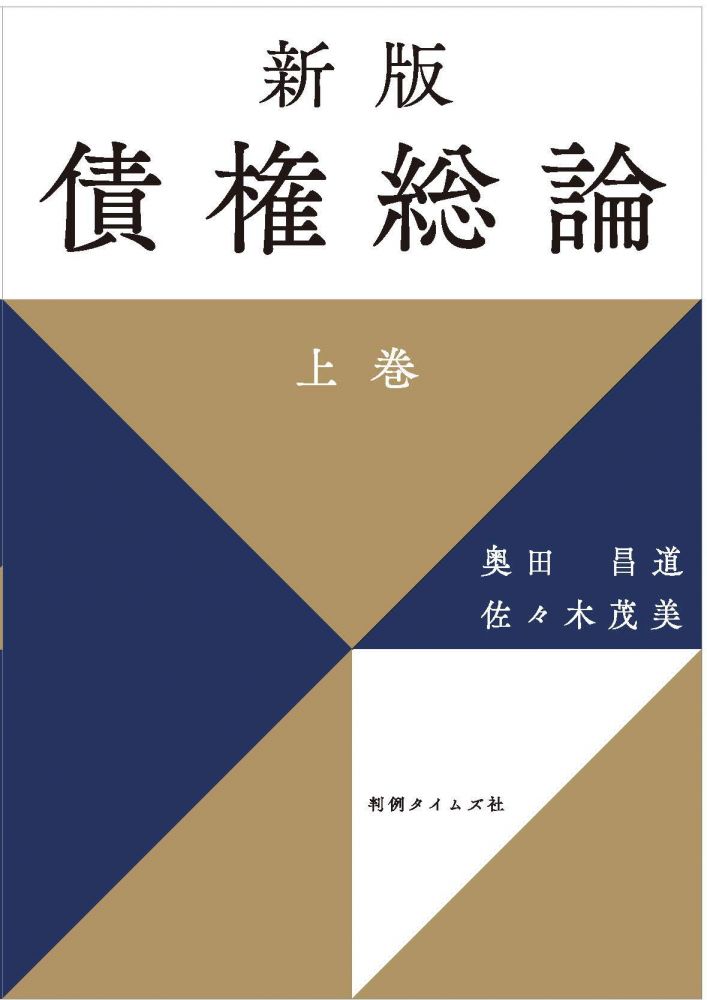
奥田昌道(高3期)、佐々木茂美(高18期)
奥田昌道(高3期)
1932年生まれ
1955年:京都大学法学部卒業
1958年:京都大学法学部助教授
1970年:京都大学法学部教授
1992年:京都大学大学院法学研究科教授
1996年:京都大学名誉教授
1999年:最高裁判所判事
2004年:同志社大学大学院司法研究科教授
同年:日本学士院会員
佐々木茂美(高18期)
1948年生まれ
1971年:京都大学法学部卒業
1974年:福岡地方裁判所判事補任官
1988年:東京地方裁判所判事
1989年:司法研修所教官
1999年:大阪地方裁判所部総括判事
2005年:京都家庭裁判所所長
2007年:大阪地方裁判所所長
2010年:司法研修所所長
2011年:高松高等裁判所長官
2012年:大阪高等裁判所長官
2013年:京都大学大学院法学研究科教授
知っておきたい爪の知識と病気
出版日2022年05月23日発行者金原出版 著者東禹彦(高7期)
ベストセラー『爪―基礎から臨床まで』の著者、東先生の簡単に手に取って読めるわかりやすい新作。日常生活においては爪そのものに原因のある病気がたくさんある。そのような爪の病気を治したり、予防するためには爪そのものについての知識をもつことが大切。身近な爪の役割や爪の切り方から爪の様々な病気まで、イラストや写真を使って原因や治療法をわかりやすく解説。爪の変化にいち早く気づき必要な対応がわかる頼れる1冊!
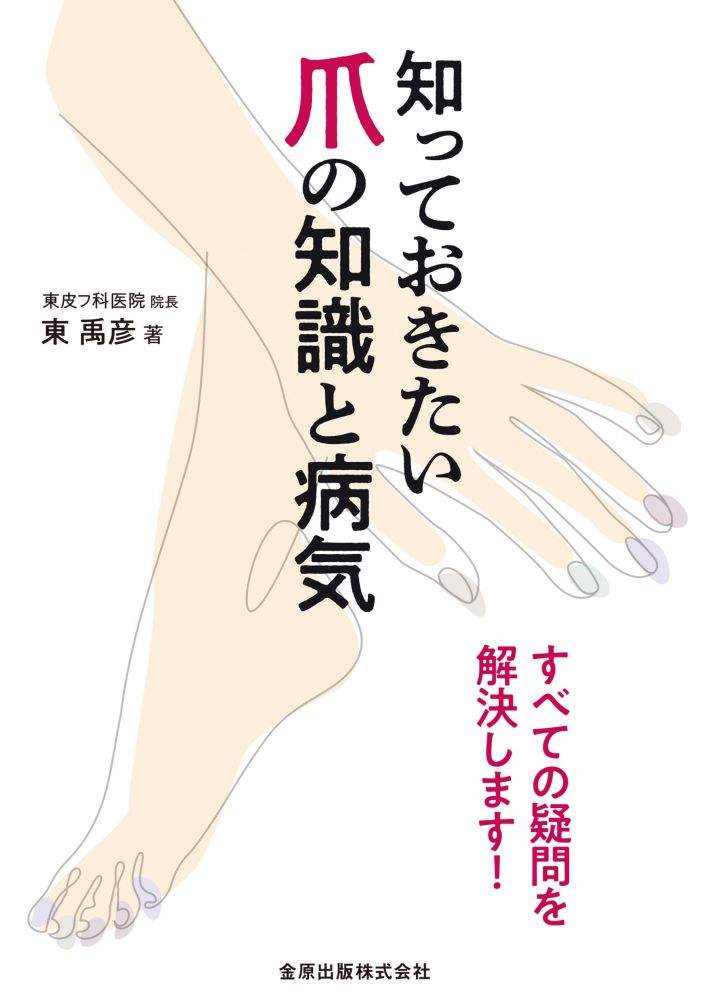
東禹彦(高7期)
東 禹彦(高7期)
昭和30年3月大阪府立八尾高校卒業。
昭和37年3月大阪市立大学医学部卒業。
昭和38年4月大阪市立大学医学部皮膚科。
昭和47年1月関西医科大学皮膚科助教授。
昭和54年9月堺市立堺病院皮膚科部長。
平成8年10月市立堺病院副院長兼皮膚科部長。
平成14年4月東皮膚科医院院長
[主な活動]
日本皮膚科学会
アレルギー学会日本医真菌学会
日本研究皮膚科学会
日本皮膚アレルギー学会
日本接触皮膚炎学会
上記学会では評議員を長年にわたり勤めた。
入門 情報リテラシー
出版日2022年04月11日発行者コロナ社 著者稲川孝司(高22期)共著
Microsoft 365/Office 2019を活用した情報リテラシーの入門書であり,大学・短期大学・高等専門学校の情報教育のテキストとして利用できる。
5章 プレゼンテーション(PowerPoint)を執筆。
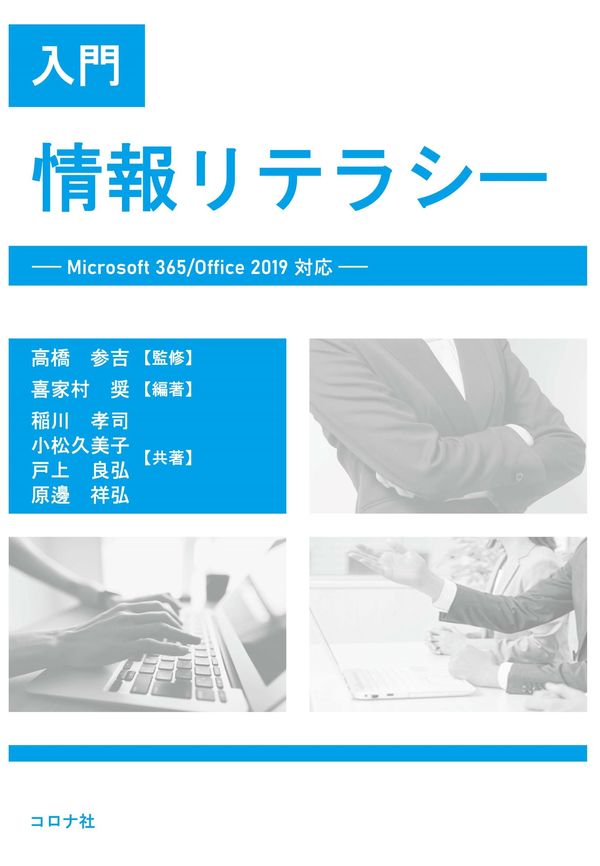
稲川孝司(高22期)共著
1974年 大阪府立大学工学部電気工学科卒業
1976年 大阪府立大学大学院工学研究科修士課程修了(通信工学専攻)
1980年 大阪府立泉北高等学校教諭
1991年 大阪府立西成高等学校教諭
2003年 大阪府立清水谷高等学校教諭
2008年 大阪府立東百舌鳥高等学校教諭
2013年 大阪府立大学非常勤講師
2014年 畿央大学非常勤講師
2018年 帝塚山学院大学非常勤講師
2019年 大阪芸術大学非常勤講師
現在に至る
情報科教育法―これからの情報科教育―
出版日2022年01月25日発行者実教出版 著者稲川孝司(高22期)共著
・2022年度実施の新教育課程に対応した情報科教育法テキストの決定版。
・学習指導要領解説編集委員、情報科教科書著者、情報科教育研究者等、情報科教育のエキスパートによる執筆。
・プログラミング学習など、大きく理数系にシフトした新教育課程のポイントを丁寧に解説。
・具体的な指導例を数多く示し、情報科の教員免許取得を目指す学生だけでなく、高校現場教員にも役立つテキスト。
本書の第3章3-4「コンピュータと情報システムにおけるプログラミング」
第7章7-2「情報社会における法規と制度」
第7章7-5「アルゴリズムとプログラミング」
第7章7-6「モデル化とシミュレーション」を執筆
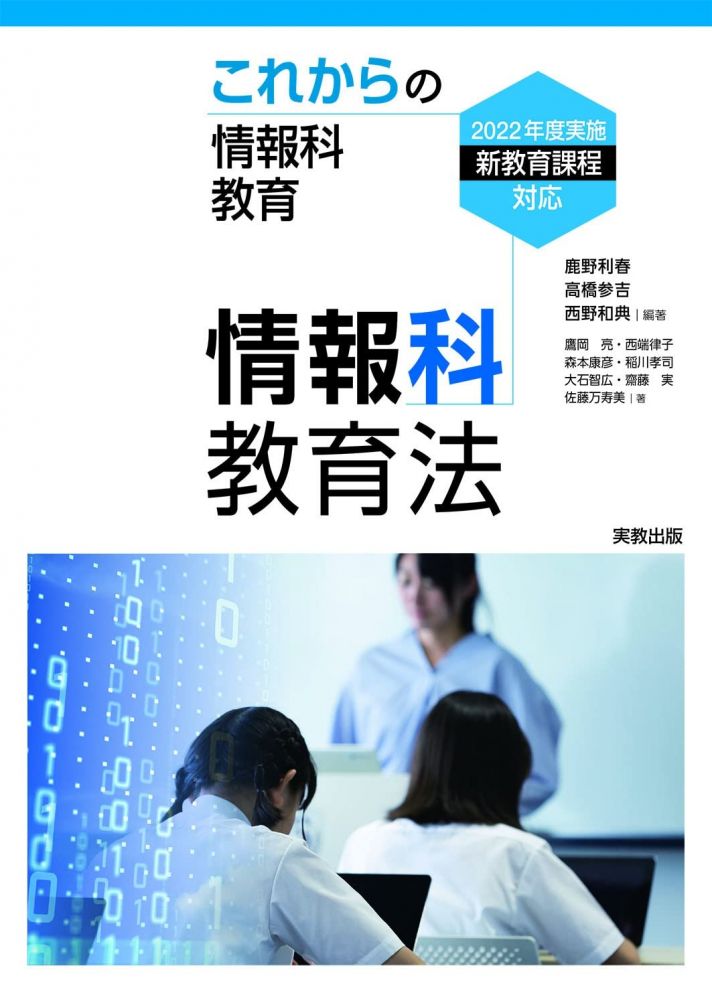
稲川孝司(高22期)共著
大阪府立大学工学部電気工学科卒業後、同修士課程修了
その後、大阪府立の高等学校で数学、情報を教える。
現在、大阪府立大学、大阪芸術大学、帝塚山学院大学で非常勤講師